美術史家(仮頁)
こちらの方の「プロジェクト「」ページであるが、古くて広告も入りみずらいので、参考に仮保存するいずれ自作したい
、 http://arssketch.web.fc2.com/project/project10/index.html
世界の著名な美術史家一覧
※生誕年を基準に並べています。名前をクリックすると、詳細を表示できます。
| 特 徴 | イタリア |
イギリス(ヴァールブルク学派) |
イギリス |
ドイツ/スイス |
フランス |
ウィーン学派 |
アメリカ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 伝記としての美術史 | ジョルジョ・ヴァザーリ(1511-1574) |
※ハンブルグ→イギリス | |||||
| 1600 | 流派の分類 | |||||||
| 1700 | 古代への興味が考古学へ発展 | ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマン(1717-1768) ヨハン・ヴォルフガンク・フォン・ゲーテ (1749-1832) |
||||||
| 1800 | 経験主義からの鑑定法 | ジョヴァンニ・モレッリ(1816-1891) | ||||||
| 文化史としての美術史 | ジョヴァンニ・バッティスタ・カヴァルカセッレ(1820-97) | ヤーコプ・ブルクハルト(1818- 1897) | ||||||
| 1850 | フランツ・ヴィクホフ (1853-1909) | |||||||
| 自立的形式主義 | アンリ ベルグソン (1859-1941) | アロイス・リーグル(1858-1905) | ||||||
| 1860 | 様式史 | ハインリヒ・ウ゛ェルフリン(1864-1945) | エミール・ マール(1862-1954) | |||||
| 図像学研究 | アビ・ヴァールブルク(1866-1929) | ロジャー・フライ(1866-1934) | ユーリウス・フォン・シュロッサー(1866 - 1938) |
バーナード・ベレンソン(1865-1959) | ||||
| 1870 | 精神史的研究 | エルンスト・カッシーラ(1874-1945) | ウォルター・フリードレンダー(1873-1966) | エリー・フォール(1873-1937) | マックス・ドヴォルシャック(1874-1921) | |||
| 1880 | クライヴ・ベル(1881-1964) | フレデリック・アンタール(1887-1954) | アンリ・フォシヨン(1881-1943) | |||||
| 1890 | ロベルト・ロンギ(1890-1970) | フリッツ・ザクスル(1890-1948) | ヴァルター・ベンヤミーン(1892-1940) | ハル・フォスター (1892-) | ||||
| アーヴィン・パノフスキー(1892-1968) | ハーバード・リード(1893-1968) | アーノルド・ハウザー(1892-1978) | ||||||
| 図族解釈学的研究 | マリオ・プラーツ(1896-1982) | ヨーゼフ・ガントナー(1896-1947) | ハンス・ゼーデルマイヤ(1896-1984) | |||||
| 1900 | 社会学的研究 | ルドルフ・ウィットコウアー(1901-1971) | ニコラウス・ペブスナー(1902-1983) | ピエール・フランカステル(1900-1970) | オットー・ペヒト(1902-1988) | マイヤー・シャピロ(1904-1996) | ||
| ケネス・クラーク(1903-1983) | ユルギス バルトルシャイティス(1903-1988) | |||||||
| フランシス・D・クリンジェンダー(1907-1955) | グスタフ・ルネ・ホッケ (1908-1987) | ルネ・ユイグ (1906-1997) | ハロルド・ローゼンバーグ(1906-1978 ) | |||||
| 記号論 | E.H.ゴンブリッチ (1909-2001) | クロード・レヴィ=ストロース(1908- ) | クレメント・グリーンバーグ(1909-1994) | |||||
| 1910 | フォーマリズム | アンドレ シャステル(1912-1990) | ||||||
| ローレンス ゴウイング (1918-1991) | ロラン・バルト(1915-1980) | |||||||
| 1920 | フェデリコ・ゼリ(1921-1998) | ジョン・バージャー(1926-) | ||||||
| ジョセフ リクワート(1926-) | ミシェル・フーコー(1926-1984) | |||||||
| フランシス・ハスケル(1928-2000) | ユベール・ダミッシュ (1928-) | |||||||
| 1930 | ウンベルト・エーコ(1932-) | マイケル・バクサンドール(1933-) | グリゼルダ・ポロック Griselda Pollock | ピエール・ブルデュー(1930-2002) | リンダ ノックリン(1931-) | |||
| ハンス・ベルティング(1935-) | ルイ・マラン(1931-1992) | スヴェトラーナ・アルパース(1936-) | ||||||
| ピーター・バーク(1937-) | マルティン・ヴァルンケ(1937-) |
マイケル・フリード(1937-) | ||||||
| ブルース・コール(1938- ) | ||||||||
| 1940 | ジョルジョ・アガンベン(1942-) | スティーヴン・バン(1942-) | ポール・バロルスキー(1941~) | |||||
| ティモシー.J.クラーク (1943-) | ダニエル・アラス(1944-2003) | ティエリード・デューヴ(1944-) | ||||||
| ヴォルフガング・ケンプ(1946- ) | トマス・クロウ(1948- ) | |||||||
| ヴィクトル・I. ストイキツァ (1949-) | ボリス・グロイス(1947-) | ノーマン ブライソン(1949-) | ||||||
| 1950 | 記号学的研究 | ジョルジュ・ディディ=ユベルマン(1953-) | イヴ=アラン・ボア(1952-) | |||||
| 1960 | 構造主義 | タイモン・スクリーチ (1961-) | ||||||
| 1970 | フェミニスト美術史 | W.J.T. ミッチェル(不明) | ||||||
| 1980 | ニュー・アート・ヒストリー | ジョナサン・クレーリー(不明) |
美術史家(イタリア)
| 1500 | ジョルジョ・ヴァザーリGiorgio Vasari(1511-1574) 62祭没 (Wikipedia) 画家・建築家
『ルネサンス画人伝』1550年133 人、1568年第2版30人を追加 『続ルネサンス画人伝』 『 ルネサンス彫刻家建築家列伝』 『芸術家列伝1 ─ ジョット、マザッチョほか』 『芸術家列伝2─ボッティチェルリ、ラファエルロほか』 『芸術家列伝3 ― レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ 』 |
 |
|---|---|---|
| 1800 | ジョヴァンニ・モレッリGiovanni Morelli(1816-1891) (Wikipedia) 美術鑑定家 「イタリアの政治家・医師で、美術史上、作品鑑定の技術に 科学的方法を導入した研究者として知られる」 |
 |
| ジョヴァンニ・バッティスタ・カヴァルカセッレ(1820-97) Giovanni Battista Cavalcaselle(イタリア版Wikipedia) 『歴史的建築物および美術品の保全についての小冊子』1863 |
 |
|
| 1890 | ロベルト・ロンギRoberto Longhi(1890-1970) (en Wikipedia)美術史家 公式サイトhttp://www.fondazionelonghi.it/ 『イタリア絵画史』 『芸術論叢(1)アッシジから未来派まで 』 『芸術論叢 (2) 』 岡田 温司 (訳) |
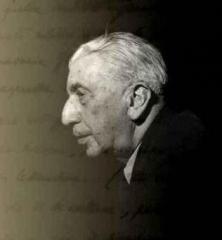 |
| マリオ・プラーツMario Praz(1896-1982) 美術史家、文学研究者 (Wikipedia) 『肉体と死と悪魔―ロマンティック・アゴニー』 『ペルセウスとメドゥーサ―ロマン主義からアヴァンギャルド』 『ローマ百景―建築と美術と文学と』 『官能の庭』 『ムネモシュネ―文学と視覚芸術との間の平行現象』 『綺想主義研究―バロックのエンブレム類典』 『蛇との契約―ロマン主義の感性と美意識』 |
 |
|
| 1920 | フェデリコ・ゼリFederico Zeri(1921-1998) (it.wikipedia.) 『 イメージの裏側―絵画の修復・鑑定・解釈』 |
 |
| 1930 | ウンベルト・エーコUmberto Eco(1932-2016) (Wikipedia)哲学者、小説家、ボローニャ大学教授。記号論の研究 『 薔薇の名前』1980 『 美の歴史』2005 『 醜の歴史 』 『芸術の蒐集』 『異世界の書―幻想領国地誌集成』 |
 |
| 1940 | ジョルジョ・アガンベンGiorgio Agamben(1942-) 『幼児期と歴史―経験の破壊と歴史の起源』 『 ホモ・サケル―主権権力と剥き出しの生』 『 中味のない人間 』 『 アウシュヴィッツの残りのもの―アルシーヴと証人』 『開かれ―人間と動物 』 『スタンツェ―西洋文化における言葉とイメージ 』 松岡正剛の千夜千冊/1324 |
 |
| ヴィクトル・I. ストイキツァVictor I. Stoichita (1949-) (fr.wikipedia) 『絵画の自意識―初期近代におけるタブローの誕生』 『 ゴヤ―最後のカーニヴァル』 『ピュグマリオン効果―シミュラークルの歴史人類学』 『幻視絵画の詩学―スペイン黄金時代の絵画表象と幻視体験』 『影の歴史』 |
※講演会写真記録 http://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/ |
ウォーバーグ(ウ゛ァールブルグ)美術史家
| 1500 | ||
|---|---|---|
| 1600 | ||
| 1700 | ||
| 1800 | ||
| 1850 | ||
| 1860 | アビ・ヴァールブルク(1866-1929)こちらもどうぞ |
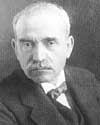 |
| 1870 | エルンスト・カッシーラ(1874-1945) こちらもどうぞ Ernst Cassirer 新カント派 ハンブルク大学教授、アメリカ合衆国に亡命 『シンボル形式の哲学』3巻(1923、1925、1929) |
 |
| 1880 | ||
| 1890 | フリッツ・ザクスル(1890-1948) Fritz Saxl 美術史家・文化史家。ウィーンのユダヤ人家庭に生まれる。ウィーン大学でドウ゛ォルジャークに、ベルリン大学でウ゛ェルフリンに師事。ウ゛ァールブルクの秘書、研究所の初代所長を努め、文庫・研究所のロンドン移転および発展に尽力。 『シンボルの遺産』 『英国美術と地中海世界』 |
 |
| アーヴィン・パノフスキー(1892-1968) こちらもどうぞ Erwin Panofsky ユーリウス・フォン・シュロッサーに学ぶ。ハンブルク大学教授、アメリカ合衆国に亡命 『イコノロジー研究』1939 |
 |
|
| 1900 | ルドルフ・ウィットコウアー(1901-1971) Rudolf Wittkower パノフスキーの理論を建築に応用 『数奇な芸術家たち―土星のもとに生まれて』、『彫刻―その制作過程と原理』など |
 |
| E.H.ゴンブリッチ (1909-2001) こちらもどうぞ Ernst H. Gombrich オーストリア生まれ、ロンドンに亡命。のちにイギリスに帰化。ヴァールブルク研究所に勤務 『芸術と幻影』、『シンボリック・イメージ』など |
 |
|
| 1910 | ||
| 1920 | ||
| 1930 | マイケル・バクサンドール(1933-) |
イギリス美術史家
| 1500 | ||
|---|---|---|
| 1600 | ||
| 1700 | ||
| 1800 | ||
| 1850 | ||
| 1860 | ロジャー・フライ(1866-1934) Roger Fry 『セザンヌ論』などポスト印象派の紹介、ほかフォーマリズム批評家 |
 |
| 1870 | ||
| 1880 | クライヴ・ベル(1881-1964) Clive Bell 『アート』1914 フォーマリズムの理論書 |
 |
| 1890 | ハーバード・リード(1893-1968) Herbert Edward Read 『芸術と疎外―社会における芸術家の役割』 |
 |
| 1900 | ニコラウス・ペブスナー(1902-1983) Nikolaus Pevsner ドイツ生まれで、のちにイギリスに亡命 『英国美術の英国性』 |
 |
| ケネス・クラーク(1903-1983) Kenneth M.Clark 『芸術と文明』1969 『絵画の見方』 『風景画論』 『ザ・ヌード』 『ヒューマニズムの芸術』 ピエーロ・デッラ・フランチェスカを近代的な形式主義者として扱う。 |
 |
|
| フランシス・D・クリンジェンダー(1907-1955) Klingender, Francis D 歴史家 |
||
| 1910 | ローレンス ゴウイング (1918-1991) Lawrence Gowing 画家・美術史家 『ルーヴル美術館の絵画』 |
 |
| 1920 | ジョン・バージャー(1926-) |
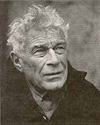 |
| ジョセフ リクワート(1926-) Joseph Rykwert ワルシャワ(ポーランド)生まれ。1939年イギリスに移住。 『アダムの家―建築の原型とその展開』 |
 |
|
| フランシス・ハスケル(1928-2000) Francis Haskell 美術史家 イタリアのパトロン制度などの研究 |
 |
|
| 1930 | グリゼルダ・ポロック (不明) Griselda Pollock 『視線と差異―フェミニズムで読む美術史』 |
|
| ピーター・バーク (1937-) Peter Burke 歴史家、英・ケンブリッジ大学名誉教授。イマニュエルカレッジの名誉校友(フェロー)。オックスフォード大学卒業後、同大学聖アントニーカレッジで研究、博士論文執筆中にサセックス大学に招聘される。同大学で16年間の教員勤務の後、ケンブリッジ大学に移り、文化史講座教授を長く担任。 New Cultural History を提唱し、「文化史」概念を刷新。ヨーロッパ史家、文化史家として世界的に著名な歴史家。 『イタリア・ルネサンスの文化と社会』 『知識の社会史―知と情報はいかにして商品化したか』 『時代の目撃者―資料としての視覚イメージを利用した歴史研究』 |
 |
|
| 1940 | スティーヴン・バン(1942-) Stephen Bann マンチェスター生まれ。ブリストル大学教授。 カンタベリー・ケント大学教授、同大学現代文化研究所所長でもあった。 怪物の黙示録―『フランケンシュタイン』を読む |
 |
| ティモシー.J.クラーク (1943-) Timothy J. Clark |
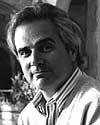 |
|
| 1960 | タイモン・スクリーチ (1961-) Timon Screech 英国バーミンガム生まれ。 1985年、オックスフォード卒業。1991年ハーヴァード大学博士課程修了。現在ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院(SOAS)助教授、日本美術史。国際交流基金スカラー、朝日フェローを受けて日本留学。「ニュー・アート・ヒストリー」の方法論と光学・機械・身体論という視点の新しさによって江戸文化論に新しい局面を開こうとしている。 『江戸の大普請 徳川都市計画の詩学 』 『春画―片手で読む江戸の絵 』 『大江戸異人従来』 『大江戸視覚革命―十八世紀日本の西洋科学と民衆文化 』 『トレンド英語日本図解』 『江戸の思考空間 』 『江戸の英吉利熱―ロンドン橋とロンドン時計 』 |
ドイツ/スイス美術史家
| 1500 | ||
|---|---|---|
| 1600 | ||
| 1700 | ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマン(1717-1768) Johann Joachim Winckelman 考古学者,学芸員,古美術調査官 『ギリシャ芸術模倣論』1755年 『古代美術史』1764年 ギリシャ美術を賛美。芸術は自然を理想化すべきものであり、古代ギリシャにおいて達成されたとする。 芸術家の歴史ではなく、芸術の歴史を著した(文化史の展開)。 啓蒙主義の思想を反映 |
 |
| ヨハン・ヴォルフガンク・フォン・ゲーテ (1749-1832) Johann Wolfgang von Goethe 『ドイツの建築について』(1772) ゴシックが、ほかのあらゆる時代の建築と同様に尊敬に値するものだと論じる。 |
 |
|
| 1800 | ヤーコプ・ブルクハルト(1818- 1897) Jacob Burckhardt バーゼル大学教授 歴史家。ランケに師事 『イタリア・ルネサンスの文化』1860年 ルネサンスが中世から断絶した時期ではなく、中世人による古典文化の復興の時期と説く。 形而上学と経験主義の双方の長所を理解し利用した文化史家。 ヴァールブルクへの影響。 |
 |
| 1850 | ||
| 1860 | ハインリヒ・ウ゛ェルフリン(1864-1945) Heinrich Woelfflin バーゼル大学でブルクハルトの後継となる。 『美術史の基礎概念』1915年 初期、古典期、バロック期からなる周期モデルを提案。 様式分類の5つの対概念でルネサンス美術とバロック美術を対比。 ブルクハルトに師事しながら、形式面の研究。 |
 |
| 1870 | ウォルター・フリードレンダー(1873-1966) Walter Friedlaender ドイツでパノフスキーの師であったが、ナチスの迫害でアメリカへ亡命、 『プッサン』 『マニエリスムとバロックの成立』 |
|
| 1880 | フレデリック・アンタール(1887-1954) Frederick Antal ハンガリー 『フィレンツェ絵画とその社会的背景』 |
|
| 1890 | ヴァルター・ベンヤミーン(1892-1940) |
 |
| アーノルド・ハウザー(1892-1978) Arnold Hauser ハンガリーの歴史家 『マニエリスム 上―ルネサンスの危機と近代芸術の始源 (1)�』 『マニエリスム 中―ルネサンスの危機と近代芸術の始源 (2)�』 『マニエリスム 下』 |
 |
|
| ヨーゼフ・ガントナー(1896-1947) Joseph Gantner バーゼル大学でウ゛ェルフリンに師事。日本では、中村 二柄教授による論文「ヨーゼフ・ガントナーの美術史学」あり。 『芸術と社会』 『心のイメージ―美術における未完成の問題』 『レオナルドの幻想(ヴィジョン)―大洪水と世界の没落をめぐる』 『レンブラント』 |
 |
|
| 1900 | グスタフ・ルネ・ホッケ (1908-1987) Gustav Rene Hocke ブリュッセル生まれ。ボン大学でロベルト・クルティウスについて哲学博士号を取得 『迷宮としての世界』 |
 |
| 1910 | ||
| 1920 | ||
| 1930 | ハンス・ベルティング(1935-) |
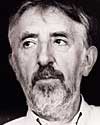 |
| マルティン・ヴァルンケ(1937-) Martin Warnke ブラジル生まれ。ミュンヘン、ベルリンで美術史、歴史、ドイツ文学を学ぶ。1964年、博士号、1970年、大学教授資格を得る。1971-79年、マールブルク大学美術史教授。1978年からハンブルク大学教授。彼の主張する「批判的美術史 Kritische Kunstgeschichte」の方法は、芸術作品を成立させる諸要素を政治的・イデオロギー的観点から解釈しようとするものである。 『政治的風景―自然の美術史』 『クラーナハ「ルター」―イメージの模索����作品とコンテクスト』 |
 |
|
| 1940 | ヴォルフガング・ケンプ(1946- ) Wolfgang Kemp ハンブルグ大学教授 『レンブラント『聖家族』―描かれたカーテンの内と外�』 |
 |
| ボリス・グロイス(1947-) Boris Groys 『全体芸術様式スターリン』 |
 |
フランス美術史家
| 1500 | ||
|---|---|---|
| 1600 | ||
| 1700 | ||
| 1800 | ||
| 1850 | アンリ ベルグソン (1859-1941) Henri Bergson 哲学/文学博士 『物質と記憶』、『時間と自由』、『創造的進化』、『道徳と宗教のニ源泉』 現象学の先駆け。直観によってこそ生きた現実が把握されるとする独自の経験論を確立 |
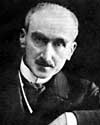 |
| 1860 | エミール・ マール(1862-1954) Emile Male 美術史家 『ヨーロッパのキリスト教美術』、 『ロマネスクの図像学』、 『ゴシックの図像学』、 『中世末期の図像学』など |
 |
| 1870 | エリー・フォール(1873-1937) Elie Faure 臨床医/生物学者/美術史家 『形態の精神』 |
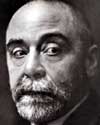 |
| 1880 | アンリ・フォシヨン(1881-1943) Henri Focillon 形式主義的美術史学派 『かたちの生命』1974 『ピエロ・デッラ・フランチェスカ』1974 「形は生きて芸術として存在する」 |
 |
| 1890 | ||
| 1900 | ピエール・フランカステル(1900-1970) Pierre Francastel 芸術社会学のフランス学派 『絵画と社会』、 『人物画論』、『 芸術の社会学的構造 形象の解読』、『形象と場所-クァトロチェンとの視覚秩序』1967 社会集団の枠内での作品解明 |
|
| ユルギス バルトルシャイティス(1903-1988) Jurgis Baltrusaitis リトアニア生まれの美術史家。アンリ・フォシヨンの娘婿 『アナモルフォーズ�』 、 『鏡����バルトルシャイティス著作集�』 、 『幻想の中世』など |
 |
|
| ルネ・ユイグ (1906-1997) Rene Huyghe 『かたちと力』 |
 |
|
| クロード・レヴィ=ストロース(1908- ) Claude Levi-Strauss 文化人類学者。ベルギー、ブリュッセル生まれ。 両親はユダヤ家フランス人で、生後間もなくパリに戻った。41年ににアメリカへ亡命。ニューヨーク「社会調査のための新学院」に招かれ、ブルトンやエルンストらの亡命中のシュルレアリスト、言語学者のヤコブソンと出会う。 記号論で芸術を読み解いた。 『野生の思考』 |
 |
|
| 1910 | アンドレ シャステル(1912-1990) Andre Castel 美術史・文化史家 『ルネサンス精神の深層』、 『グロテスクの系譜』、 『ルネサンスの危機―1520-1600年』 |
 |
| ロラン・バルト(1915-1980) Roland Barthes 記号学者、思想家。 『零度のエクリチュール』 『美術論集─アルチンボルドからポップ・ア-トまで』 |
 |
|
| 1920 | ミシェル・フーコー(1926-1984) Michel Foucault ポスト構造主義の代表的哲学者 『言葉と物』 『知の考古学』 |
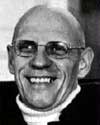 |
| ユベール・ダミッシュ(1928-) Hubert Damisch パリ大学にてモーリス・メルロ=ポンティの指導もと哲学を修める。ジャズ・ミュージシャンとしての活動やユネスコ勤務を経て、1967年から高等師範学校の教壇に立ち、続いて1975年から1996年までパリの社会科学高等研究院で美術史を講じていた。 『パリスの審判―美と欲望のアルケオロジー』 『スカイライン : 舞台としての都市』 |
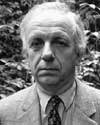 |
|
| 1930 | ピエール・ブルデュー(1930-2002) Pierre Bourdieu 社会学者 『ディスタンクシオン』 同時代の同意文化圏において芸術的価値観や趣味は、個人の生得的傾向や自由な判断に属する物ではなく、階級や職業、教育水準の関数として社会的に規定されていることを示す。 |
 |
ルイ・マラン(1931-1992) |
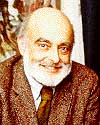 |
|
| 1940 | ダニエル・アラス(1944-2003) Daniel Arasse アルジェ生まれ。 高等師範学校を出たのち、古典古代文学の大学教授資格を取得。パリ第四大学やパリ第一大学などの教壇を経て、1993年からはパリの社会科学高等研究院で美術史を講じていた。パリにて59歳で逝去。 『 なにも見ていない―名画をめぐる六つの冒険』 『ギロチンと恐怖の幻想 』 『モナリザの秘密―絵画をめぐる25章 』 |
 |
| 1950 | ジョルジュ・ディディ=ユベルマン(1953-) Georges Didi-Huberman イメージの多層性、その錯綜した時間性(アナクロニスム)を、哲学、人類学、精神分析学などの視点を往還しながら考察している美術史家。パリの社会科学高等研究院で美術史を講じる。 『フラ・アンジェリコ 神秘神学と絵画表現』 『ヴィーナスを開く―裸体、夢、残酷』 『ジャコメッティ―キューブと顔』 |
 |
ウィーン美術史家
| 1500 | ||
|---|---|---|
| 1600 | ||
| 1700 | ||
| 1800 | ||
| 1850 | フランツ・ヴィクホフ (1853-1909) Franz Wickhoff 『ウィーン創世記』 |
 |
| アロイス・リーグル(1858-1905) Alois Riegl オーストリア、リンツ生まれ。83年にオーストリア歴史研究所勤務を経て86年、ウ゛ィクホフの後任としてオーストリア美術工芸博物館美術部門の部長に就任。89年に大学教授資格を取得、97年にはウィーン大学の正教授として招聘される。形式主義学派 『美術様式論』 美術の歴史は普遍法則に支配されると考える。 芸術作品はおのおのの時代に特有の芸術的意志の結果とする。 |
 |
|
| 1860 | ユーリウス・フォン・シュロッサー(1866 - 1938) Julius Von Schlosser 『美術史「ウィーン学派」』 |
 |
| 1870 | マックス・ドヴォルシャック(1874-1921) Max Dvorak 『精神史としての芸術史』 精神史 観念と歴史のあいだの関係 エル・グレコを先駆的な表現主義者として扱う。 |
 |
| 1880 | ||
| 1890 | ハンス・ゼーデルマイヤ (1896-1984) Hans Sedlmayr 『光の死』 『大聖堂の生成』 |
 |
| 1900 | オットー・ペヒト(1902-1988) Otto Pacht 『美術への洞察』 |
 |
| 1910 | ||
| 1920 | ||
| 1930 |
アメリカ美術史家
| 1500 | ||
|---|---|---|
| 1600 | ||
| 1700 | ||
| 1800 | ||
| 1850 | ||
| 1860 | バーナード・ベレンソン(1865-1959) |
 |
| 1870 | ||
| 1880 | ||
| 1890 | ハル・フォスター(1892-) Hal Foster プリンストン大学 『反美学―ポストモダンの諸相』 『視覚論』 |
 |
| 1900 | マイヤー・シャピロ(1904-1996 ) Meyer Schapiro リトアニア生まれ。アメリカへ移住。 『様式』※ゴンブリッチとの共著、 『セザンヌ』、 『ゴッホ』、 『モダン・アート』など、アメリカ現代美術を最初に評価。 フランドルの祭壇画を精神分析の手法で分析 人類学的な美術史家で、美術の社会史的研究を発展。 |
 |
| ハロルド・ローゼンバーグ(1906-1978 ) Harold Rosenberg 『アートニューズ』誌でアクションペインティングを命名 |
 |
|
| クレメント・グリーンバーグ(1909-1994) Clement Greenberg ニューヨーク、ブロンクス生まれ。 抽象表現主義の画家たちとの交流をとおし、独特のモダニズム絵画論を構築。 『芸術と文化』 |
 |
|
| 1910 | ||
| 1920 | ||
| 1930 | リンダ ノックリン(1931-) Linda Nochlin ニューヨーク、ブルックリン生まれ。 『絵画の政治学』 美術史にジェンダーの視点をもたらす |
 |
| スヴェトラーナ・アルパース(1936-) Svetlana Alpers バークレイ大学 Berkeley Universityの美術史教授で、 17 世紀のオランダ美術のスペシャリスト 『描写の芸術―一七世紀のオランダ絵画』 |
 |
|
| マイケル・フリード(1937-) Michael Fried モダニズムを擁護 |
 |
|
| ブルース・コール(1938- ) Bruce Cole カリフォルニア大学教授 中世・ルネサンス研究 『ルネサンスの芸術家工房』 |
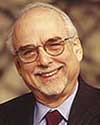 |
|
| 1940 | ポール・バロルスキー(1941~) Paul Barolsky ミドルベリー大学を卒業後、ハーバード大学で博士号を取得。1969年からヴァージニア大学に奉職。現在、美術史学教授。イタリア・ルネサンスの専門家 『とめどなく笑う―イタリア・ルネサンス美術における機知と滑稽』 『芸術神ミケランジェロ―鼻の神話と隠された自伝』 『庭園の牧神―ミケランジェロとイタリア・ルネサンスの詩的起源』 |
 |
| ティエリード・デューヴ(1944-) Thierry De Duve ベルギーのシントトリュイデン生まれ。ブリュッセルおよびアメリカ在住。欧米を舞台に活躍している現代の代表的な美術史家。ブリュッセルのルーヴェン大学で哲学、心理学を修め、パリの社会科学高等研究学院の博士課程でルイ・マランに師事し博士の学位を取得。ブリュッセルでジャン・ギローとともにグラフィック研究学院を創立し教授となり、その後、欧米各地の大学の学部ならびに大学院において、特別招聘教授として芸術史、現代絵画、美学等の講義をおこなう。また欧米各地の美術館等において、「マルセル・デュシャン展」、「キネティック・アート展」など数々の特別美術展の企画責任者として活躍。美術や芸術の国際学会の主宰をはじめ学会活動もめざましく、多くの論文、評論等がある 『マルセル・デュシャン―絵画唯名論をめぐって 』 『芸術の名において―デュシャン以後のカント/デュシャンによるカント』 |
 |
|
| トマス・クロウ(1948- ) Thomas Crow 美術史家 ゲッティ・センター ディレクター |
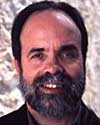 |
|
| ノーマン ブライソン(1949-) Norman Bryson 英国生まれ。ケンブリッジ大学、カリフォルニア大学、ロンドン大学で英米文学と美術史を専攻。 『美術とジェンダー』 記号論、文学批評など。 |
 |
|
W.J.T. ミッチェル(不明) |
 |
|
| ジョナサン・クレーリー(不明) Jonathan Crary コロンビア大学教授 『知覚の宙吊り―注意、スペクタクル、近代文化』 |
||
| 1950 | イヴ=アラン・ボア(1952-) Yve‐Alain Bois ハーヴァード大学教授(近代美術史)。マチス、ピカソから戦後アメリカ美術、特にミニマル・アートにいたる20世紀美術について幅広く研究 『マチスとピカソ』 |
 |